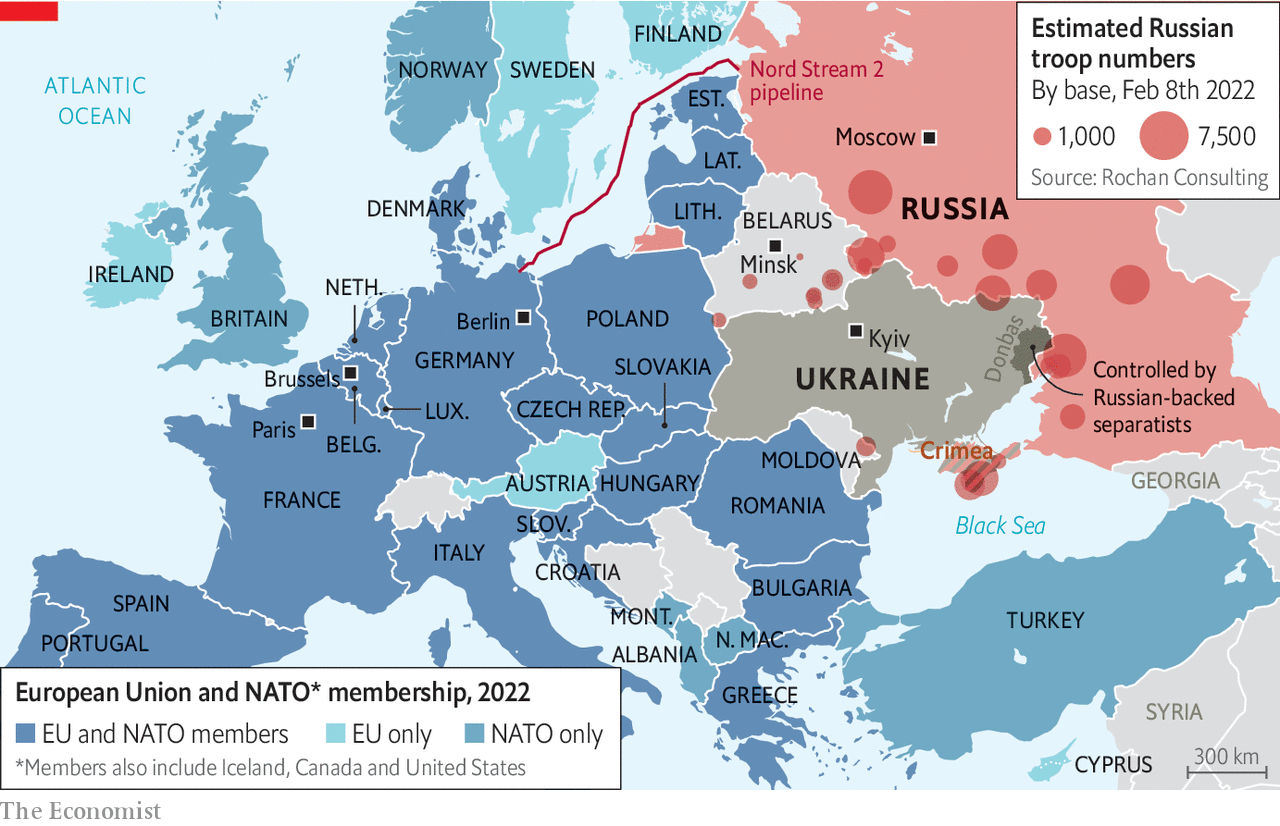The Economist の 2 月 24 日号から TSMC の日米で稼働予定の新工場についての記事が載っていましたのでご紹介します。
曰く、TSMC のチップ製造工場は日本の熊本県と米国のアリゾナ州で稼働予定ですが、双方の進捗具合には大きな差があるとのこと。
同誌はこの違いとして、労働者(組合の影響が強く許認可に時間がかかったアリゾナ州)、パートナーの座組(デンソーやトヨタ、ソニーなどを含む熊本県と TSMC が 1990 年代以来初めて単独で行うアリゾナ州)、そして政府補助金(既に TSMC は日本政府からの補助金を受領済みな一方で米国政府からの補助金は審査が継続中)を挙げています。
ただし、チップ自体の性能はアリゾナ工場で製造されるものの方が最新のようです。
少し話題が逸れますが、個人的には熊本の経済、特に GDP が加速的に伸びることが予想され、人口動態から考える東京一極集中、あるいは首都圏集中が謳われる中での地方都市の期待の星として今後目が離せないと考えております。今後、同誌の中で熊本がモデルケースとして取り上げられるようになるのではないかと予想しながら、The Economist を読み続けたいです。